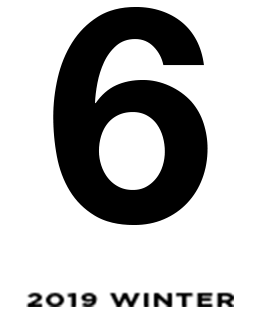青井 茂 株式会社アトム 代表取締役

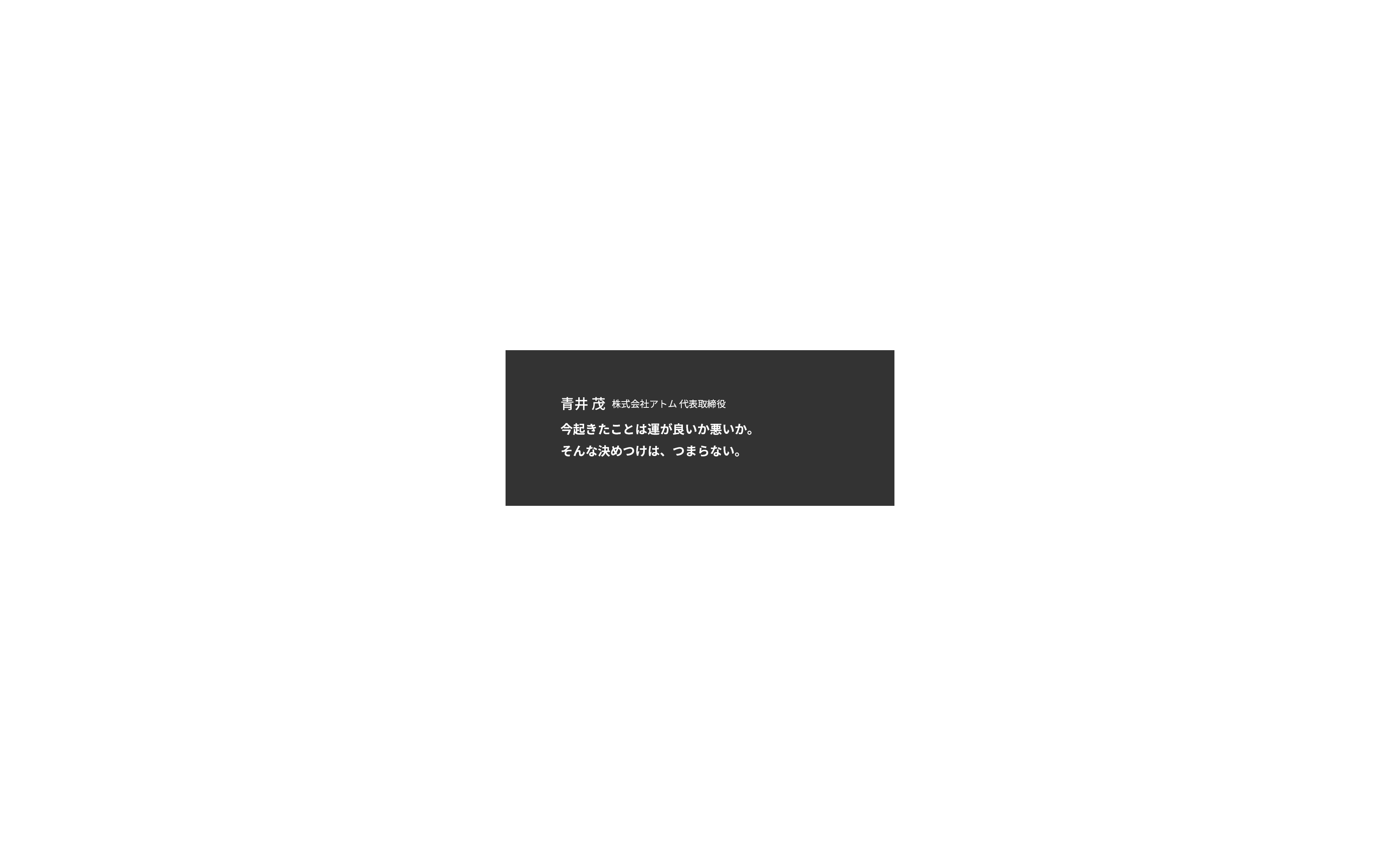
喜劇王、チャップリンの代表作に『モダン・タイムス』という映画がある。工場労働者である主人公は、終始モニターで監視されながらベルトコンベアーにへばりつき、スパナでネジを回す単純作業をひたすら繰り返している。あるとき彼は工場で騒動を起こし、精神病院送りとなるが、退院後、パンを盗んで逃げる途中の浮浪少女とたまたま知り合う。二人は何度も運命に翻弄され、絶望しながらも、手を取り合い、未来へ向けて歩き出す。そして、最後はこんな言葉で締めくくられる。「へこたれないで元気を出すんだ。運が開ける!」
僕は生まれてから今までずっと「自分は運がいい人間だ」と思っている。「一部上場企業の創業者の孫」という肩書きは、時々重くのしかかることはあったが、決して邪魔にはならなかった。大学を卒業後、数々の会社を経て、祖父が創業した会社のひとつであるA-TOMに入り、不動産の仕事をするようになってからも「運」は非常に大事な役割を果たしてきた。いい物件に当たるかどうかは、まさに運次第といっても過言ではない。もちろん、運が100%物件を見つけてくれるのではなくて、何十、何百もの物件を訪ね、比較し、検討するという作業を重ねて、ようやく巡り会いにつながるのだが、それでも日本国内に星の数ほどある物件の中で、たったひとつ、これというものに出会えるかどうかは、運が大きく関係している。
運ということについていえば、面白いエピソードがある。僕は2013年、コートヤードHIROOを競売で手に入れたが、実は、その前年に別の会社が落札して、僕はすんでのところで逃していたのだ。手付金まで払われていて、もう成す術はなくなったと悔しがっていたところ、突然、その会社がキャンセルし、物件は再び競売市場に登場した。それに僕が飛びついて、取得することができたのだ。
「運」とは一体なんだろう。僕はしばらくアメリカで暮らしたことがあるが、アメリカ人は基本的に「運がいい」という考え方をしない。というよりも、フロンティア・スピリットやアメリカン・ドリームの思考法が染み込んでいるためか、彼らは「運は自分で勝ち取るもの」と考えることが多く、「どうやったら運が開けるか」というある種、運命論的な考え方ではなくて、「どうやって運を勝ち取るか」というノウハウ論で語られることがとても多い。でも僕は日本人であり、運については何か大きな力が働いているのではないかと、取り立てて根拠もなく信じている。もしかしたら無意識の信仰心やアニミズム的な考え方が影響しているのかもしれないし、あるいは、僕がこれまでの人生で何度か大きな病気や怪我をしたことがあるからかもしれない。僕は小学校に上がる前、腎臓の病気で2カ月間ほど入院した。当時の僕は周囲にとても甘やかされて育っていて、入院の日、六人一部屋の小児病棟に足を踏み入れた瞬間のことを今でも鮮明に覚えている。「僕はこの部屋で過ごすのか」。5歳の少年なりに、そんな絶望を感じたのだ。何もかも制限されている入院生活は、わがまま放題に育った少年には苦痛でしかなかった。夜になり、見舞いに来ていた家族が帰ると途端に心細くなって、「自分はどうして生まれてきたんだろう」と、寂しさに押し潰されそうになった。部屋はいつも満床だったが、昨日まで隣のベッドで寝ていた子が、ある日、突然いなくなることもあった。そして、空っぽになったベッドには、間髪入れずにまた新しく誰かが来た。そうやって、ベッドは入れかわり立ちかわり、人によって埋められていく。人が作った穴は人が埋め、僕が今、埋めているこの穴も、僕が来る前には別の誰かが埋めていたのだろうし、僕が去った後もまた違う人が埋めるのだろう。そうやって考えたら、僕という人生は僕だけのものではなくて、延々と続く大きな命の集合体の中で、連綿と引き継がれていくものなのかもしれないと思えてきた。
そう考えれば、たった今、僕の身に起こったことが、運がいいとか悪いとかいちいち定義してまわるのは、なんてつまらないことだろうと思えてくる。これはラッキーだったけれど、こっちはアンラッキーな出来事だなんて、ひとつずつ名札をつけるように色分けすることに一体なんの意味があるのだろう。海に現れる波が一つとして同じものはないように、人生には「幸運」という波もあれば「不運」という波もある。僕は大学を卒業後にカリフォルニアへ渡り、有名なサーフブランドの創業者と生活を共にしたことがある。彼は、朝から晩まで海の話しかしない、心から自然を愛する人だった。サーファーは遠い沖を見てうねりを見つけると、急ピッチでパドルして、波がピークを迎える位置へ先回りする。でも実際は、案外いい波じゃなかったり、誰かに先乗りされていたりすることもあり、そんなときは、「まあ、また次の波があるさ」とキッパリ考えを切り替える。それができるのが、良いサーファーの条件であり、そんな風に大きなうねりの中で自然の計らいに身を任せていると、いい感じに予測や計算が裏切られ、人間は人知を超えた自然の中で生かされていることに気づくのだ。
人生には、荒波に飲まれ、嵐が通り過ぎるのを頭を下げて待つしかないときもある。昔、よくテレビで観た家族ドラマでも、取るに足りないようなドタバタ劇は日常茶飯事だったし、その渦中にいる人にとっては確かに悲劇もあるのだろうが、視聴者として全編通して見渡すと、「なんだか、あったかくていいドラマだなあ」と感じるものだ。冒頭に書いたチャップリンの『モダン・タイムス』も、一つ一つの出来事を見れば、確かに悲しみや寂しさや絶望もある。だが、「へこたれなければ運が開ける」という力強い言葉とともに映画は明るく幕を引く。これはチャップリンが晩年語った、「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇である」という言葉の象徴ではないか。悲劇の一つ一つに虫の目を向けるか、あるいは、壮大な喜劇に鳥の目を向けるか。僕はできるならいつでも俯瞰する自分自身でありたいし、鳥の目を持つことができる人こそ、地面に落ちた小さな運を見つけることができるのだと思う。
What's ART


ども。はじめまして。アートディーラーのパトリックです。縁あって、A-TOMさんとお仕事させてもらっています。アートディーラー・アドバイザーって、あまり馴染みないですか? 日本語で一番近いのは「美術商」。簡単に言えば絵画などの作品をアーティストから仕入れてコレクターに販売したり、アート市場やアーティストの情報を提供したりする仕事です。ちなみに皆さんは最近どこかでアートを見ましたか? カレンダー? ポスター? 僕が常々思うのは、日本では日常的にアートと触れる機会が少な過ぎるっていうこと。アメリカでは、あ、ちなみに私は日本人ですが赤子の時からアメリカ育ちで、ついアメリカと比較してしまうのですが、向こうではお金持ちだけじゃなくて、誰でもアートに触れられる機会がたくさんあります。たとえば地下鉄。駅の構内にブロンズ像がひっそりと置かれていたり、壁のタイルに前衛的な絵が落書きみたいに描かれていたり。アートって全然特別なものじゃないんです。そうそう、落書きと言えば“元祖落書きアーティスト”のジャン=ミシェル・バスキア。この人の絵、27歳の時ヘロインのオーバードーズで亡くなったあともどんどん値上がりして、今や100億円を超えました。100億ですよ、100億! そのきっかけとなったのがあの、ZOZOTOWNの前澤社長。2016年、彼がバスキアの絵を62億円で落札して以来、バスキアはあっという間にブルーチップ・アーティストの仲間入りを果たしたのです。でもね、こう言う人もいるわけです。「お金持ちに目をかけられたアーティストだけが本物なのか」「アーティストとして成功するかどうかは『運』なのか」って。まあ、それはもっともです。「誰に認められずとも、コツコツ日陰の道を歩いています」みたいな玄人のアーティストには、著名なコレクターやディーラーと出会うチャンスはないかもしれない。今や現代アートの巨匠でもある村上隆さんを見てもわかる通り、アーティストが彼らの目に止まるのは大抵、世界中で開催されているアートフェアなのですが、コツコツ型のアーティストは華やかな場に目もくれず、アトリエにこもり、頭を掻きむしりながらひたすら描く、修行の日々を送っています。でもね、僕の持論では「アートは運」。アーティストとしての成功は、世界のアートシーンで評価され、マーケットで高額な価格がつくことも指標のひとつだと思うんです。結局、アート界で上に行くには、どれだけたくさんのコレクターやディーラーと接点を持てるかにかかっているということ。バスキアはもちろん、ピカソだってセザンヌだって岡本太郎さんだって草間彌生さんだって、みんな積極的に自分から打って出てアピールして、運をつかむ努力をしたからこそ成功したわけです。実は世界的に影響力のあるコレクターやディーラーも同じで、たとえば日本の藝大とか著名なアート系大学の学園祭にまで出かけ、「これは!」っていう人を見つけている。そして、ただ作品の良し悪しを見るのではなくて、アーティストの人間性に惚れ込んでその作品を買うんです。恋愛と一緒ですよね。「いい出会いないかなー」ってつぶやきながら、部屋でゲームをしているだけじゃ絶対いい人は見つからないし、見た目だけじゃその人の本質はわからない。結局、アートと恋愛って同じなんですよ、Art is just like romance! アートは運。恋愛も運。そう思ったら意外とアートを見る目も変わるのでは? 日本ではアートと出会える機会が少なくて、せいぜいどこかの美術館のなんとか展に行くくらいだけど、たったひとつのアートとの出会いが人生を変えることだって、もしかしたらあるかもしれない。アメリカみたいに、日常的にアートと触れ合う機会がもっと増えたらいいなあと思うこの頃です。あ、ちなみにコートヤードHIROOでも不定期でアートの展示やっていますので、よかったらよろしく。
Bar MIZO A-TOM CO,LTD.


自分を信じ、「誠実」であるべき
溝口:大学時代、同じチームでラグビーを頑張ってきた仲間としていつも思っていたけれど、廣瀬はまさにキャプテンになるべくして生まれた男。いくつものチームでキャプテンを務めてきたんだよね。
廣瀬:はじめてキャプテンを務めたのは中学生だったとき。高校、大学、東芝、日本代表でもキャプテンをやらせてもらったね。
溝口:それだけ指名され続けたのはどうしてだと思う?
廣瀬:なんとなく思うのは成長志向かな。常に「よくなりたい」って思っていて、そういう姿を周囲に見せられるのがキャプテンに指名される理由かもしれない。でも、学生時代と社会人ではキャプテンに求められるものが違うんだよね。
溝口:どういうこと?
廣瀬:学生時代はチームで一番うまい人がキャプテンになるのが普通だったから全員納得したし、自分の理論が通用した。でも社会人チームでは外国人選手もいるし、もっとうまい人もいる。だからまとめるのに苦労することも多かったよ。
溝口:たとえば?
廣瀬:東芝では自分の前に冨岡さんがキャプテンをやって勝ち続けていた。冨岡さんは熱血系で言葉も上手。僕とはタイプが違うんだよね。
溝口:確かに廣瀬は冷静で、あまり感情を出さないよね。
廣瀬:はじめはいつも「冨岡さんならこうするはず」っていう考えが頭にあった。正直、やり辛かったね。
溝口:克服したのは?
廣瀬:キャプテン2年目かな。原点に返って、自分らしさを取り戻そうって思ったんだ。「この人、無理しているな」って感じたら周りは信頼してくれない。だから、どんなときも自分の言葉で語りかけよう、たとえ間違えることがあっても自分を信じ、誠実であり続けようって思ったんだ。
みんなでつかんだ南ア戦の奇跡
溝口:2012年、日本代表のエディー・ジョーンズヘッドコーチからキャプテンに指名されたときはどうだった?
廣瀬:ワールドカップまでは4年間。1年目の目標を「勝つ文化を作る」と決めて、みんなで「勝つチームとは、どんなチームだろう」って話したんだ。そうすると、たとえば試合前の国歌斉唱でも、「勝つチームなら誇りを持って、堂々と歌うはず」っていう具体的な行動指標が見えてきた。「いつでも万全の準備で試合に臨む」「ファンを大事にする」とかね。
溝口:日本では、ラグビーはそれほどメジャーじゃなくて、当初はワールドカップに対する関心も高くなかったよね。
廣瀬:そう、それをなんとかしたかったんだ。2〜3年目にはチームが段々強くなって、勝てるわけないと思ったウエールズにも勝つことができた。だけどそのうち、「勝つけれどなぜかラグビーが楽しくない」っていう矛盾がチームに蔓延し始めたんだ。そこで「自分たちはなんのためにラグビーをしているのか」って考えた。そうしたらメンバーから「日本のラグビーを変えたい」「憧れられる存在になりたい」っていう声が聞かれたんだ。
廣瀬:誰もが憧れる存在になるためにひたすら練習して、常勝チームを目指した。そのひたむきな努力があの、南ア戦の奇跡を呼んだんだね。
まずは「アトム・ウエイ」を見つけること
溝口:いまA-TOMはミッション「2030」を掲げ、2030年までに売上20億の会社を30個つくることを目指しているんだ。そのためには30人のリーダーが必要になるんだけど、企業のリーダーってどんな存在だと思う?
廣瀬:リーダーとキャプテンはニュアンスが違うと思うんだ。チームでいえばリーダーは監督。人事権を持ち、チームの方針を決める人だよね。一方キャプテンは、リーダーとメンバーを繋ぎながら、組織としてどう目標を達成するか考える人だと思うんだ。
溝口:なるほど、そうなるとA-TOMにはリーダーとして事業を起こしつつ、キャプテンとして仲間を導いていく、二つの顔を持った人材が必要になるのかな。
廣瀬:そもそもリーダーとキャプテンは見ている世界が違うよね。リーダーは少し先の将来を見据えて指針を示すけれど、キャプテンは「今」を見て、やるべきことを考える。だけど、キャプテンはリーダーと同じ目線も必要で、リーダーの考えをわかりやすくメンバーに伝えることも役割だと思うんだ。
溝口:目標達成のためのアプローチが違うんだね。
廣瀬:そう。僕が感じるいいチームとは、そのチームの“カラー”や”イズム”があること。そして、メンバーがチームに対してロイヤリティを持っていること。チームの中で自分にしかできない役割があり、自分は替えのない存在なのだと実感できれば、誰でもチームのために全力を尽くしたいと思うよね。企業でも同じだと思う。
溝口:会社としての“イズム”は大事だよね。A-TOMは今、60代以上のベテラン社員が頑張る一方、若手社員も増えていて、歴史的に見れば過渡期といえるかもしれない。働き方に対する考え方や物事の価値観もさまざまだから、まずは「2030」を実現するための土台として、”アトムのイズム”を共有することが必要なんだね。
廣瀬:全日本ラグビーチームでも、エディは「ジャパン・ウエイ」をチームの方針として掲げた。日本人の特徴は信頼や忠誠心、努力。「それらを生かし、外国のコピーではなく日本独自のラグビーをするチームにならなければならない」という考えをメンバーに徹底したんだ。だから日本は世界の舞台で勝てた。企業も同じく、「自分たちだからこそできること」を考え、それを信じてやり抜くことができたら、必ず結果がついてくると思うんだ。
溝口:まずは、「アトム・ウエイ」を作り、それを社員が文化として共有する。そういう土台があるからこそ一人一人が会社にコミットし、能力を最大限発揮できるんだね。もう一度、自分たちが誰のために、何をする会社なのか。原点から考えてみる必要がありそうだ。