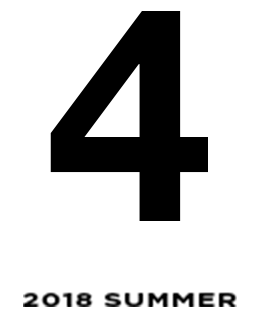青井 茂 株式会社アトム 代表取締役


僕はこの会社に入る前、企業再生の会社にいた。20代後半の頃だ。事業を再生すべき会社はたいてい地方の企業だったから、必然的に僕も1年の3分の2を東京から離れて過ごすことになった。しかし今だからこそ言えるが、僕は誰も知り合いのいない田舎で働くことがとてもいやだった。日本全体が狂喜乱舞したバブルの時代はすでに終わっていたけれど、東京ではまだ華やかな時代の名残が感じられ、六本木のど真ん中には巨大な街が出現し、だだっ広いお台場の埋立地には綺麗な砂浜やテレビ局が現れた。僕は、そんな東京を離れることが本当にいやだったのだ。毎週末、飛行機や新幹線の窓から東京のネオンが見えるたびにホッとした。
しかし、地方でのプロジェクトが終わり、東京へ戻ると決まったころには、なぜか東京の異様さが気になるようになった。どこまでも高いビルが建ち並び、無限に膨張し続ける街。その底なしの不気味さが、一旦東京を離れた僕にはとても気味悪く感じられた。
それ以来、僕にとって仕事と生活の拠点は東京だ。だが以前、ずっと東京に住んでいたころには感じられなかった居心地の悪さを、常に感じるようになってしまった。僕にはその理由がわかる。なぜなら日本では東京を中心にして“エセ資本主義”が出回っていて、誰もが閉塞感を感じつつも、目の前の作業に追われているからだ。
日本は資本主義の国だというが、僕は本当にそうかと思う。日本が今、資本主義と呼んでいるものは、アメリカから輸入したキャピタリズムだ。力があるものは数字を叩き出し、数字を出せないものは使われる立場になる。資本主義は極論を言えば、搾取するか、されるかのどちらかしかないから、こうした構造は当然だが、そもそもシビアな資本主義は日本人の性に合わない。小さな村の中で、人の和を大切にする日本人は、江戸時代の封建制で嫌というほど「搾取する側」と「される側」という関係性を経験した。その後、明治で日本は開国し、大戦後に「資本主義」が流入したが、元来、DNAレベルで「ビジネス」や「キャピタリズム」という外来語が馴染まない性分なのだ。経済と道徳。利益と貢献。そのバランスを本質的に求めている。「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」と、早々に二宮尊徳も見抜いている。
だが現代の日本人は、結果重視のシビアな資本主義に徹することができず、ビジネスからわざと人間性を欠落させてもやはり馴染まず、理想と現実の間でもがいているように見える。しかし、もともとビジネスという言葉はcareから派生したという。「ビジネスとは人が人を気にかけて働くこと」と定義するなら、僕はこれを、「どれだけ稼ぐかだけでなく、誰と稼ぐかも大事」と解釈する。そう考えれば財務諸表には現れない、企業の価値や存在意義があるはずだ。
ここ数年、僕らの会社A-TOMは東京を舞台に事業を興していない。人と建物で埋めつくされた東京には新しいことを生み出す余白がなく、地方の方がずっと面白いことができそうだからだ。だから今は、地方で事業を興すことに興味を持ち、一緒に楽しい仕事ができそうな仲間と共に、夢を現実に変えるためのレールを敷く作業に取り組んでいる。しかし最近では、エセ資本主義が地方にも進出していて、外国生まれのコーヒーショップや、アウトレットモールさえ作れば、どこでも人が集まってくると勘違いする人がとても多い。そんな安易な考えでの開発はもういい加減、やめにしないかといつも思う。
そうした考えでは、100年もつ街を創るのは到底無理だ。巨大なモールができれば地元の商店街は廃れて街の様相は大きく変わり、当初は活気のあったモールも、近隣の商業施設との戦いに負けて撤退することもあるだろう。市場を競い、共食いする。これでは魅力ある街づくりなどできるはずがない。その点、ヨーロッパの街づくりはこれからの日本のモデルとなる。地元の人たちはチェーン店でコーヒーを飲まず、経営者を知っているカフェを使う。スーパーで産地のわからない野菜を買わず、生産者が自慢の農産物を売るマルシェへ行く。それが何百年も続く街のスタイルで、お金のまわり方なのだ。手っ取り早く利益をあげたいなら、巨大資本のチェーン店を街へ招けば大金が動くだろう。だがそれでは、その街の財産にもプライドにもならない。都市部で通用した成功の方程式は、必ずしも地方都市で通じるわけではないのだ。
東京の真ん中にある明治神宮は、100年後の未来を荒野に描いて創られたという。当時の為政者が目指したのは、今後、人が手をかけなくても半永久的に続く森だった。その“永遠の森”を作るため、彼らは綿密に未来予想図を描いたのだ。僕は、街づくりもこれと同じだと思う。木を育て、葉を茂らせるには時間がかかる。だが、その木陰で数十年後に人が集い、笑い、語り合う、そんな様子を思い描いて荒野に1本ずつ苗を植える。森も街も、将来そこで暮らす誰かのために築き、遺していく財産だと思えば、僕らが考えるべき設計図は明らかだ。
僕は、祖父から受け継いだ遺伝子がそうさせるのか、祖父の生まれ育った富山が好きだ。富山で事業を興してもっと街を輝かせたいし、なんなら住まいを移してもいい。うまい空気を吸って暮らし、うまい水を飲んで死にたい。そして、未来の人たちにもそういう幸せな暮らしのバトンを手渡したい。こんな単純な理由のためだとしても、地方を愛し、事業を始め、土地の人々と暮らすことを夢見る価値は十分にある。
木下斉×國領二郎


この国には、子どもたちをビジネスの冒険に連れ出す大人が、もっと必要だ。
1.日本に古くから伝わる茶道や武道の修行では、通常、弟子は「守破離」のステップを踏む。まずは、師の教えや技を忠実に守り、確実に身につける「守」、他の流派からも良いものを取り入れ、さらに発展させる「破」、そして流派から離れ、独自に新しいものを生み出す「離」。こうした考え方は人間形成や教育においても通じるが、日本の学校システムでは「守」にばかり重点が置かれ、既定路線から外れた子どもは途端に異端児扱いされてしまう。「たとえば、学級委員はみんなの意見を平等に聞き、まとめる能力を要求される。でも本来リーダーとは折衷案を考えるのではなく、自分の意見を堂々と表明するべきもの。日本ではそうした能力を養う土壌がない」。木下斉氏はそう話す。
2.近年、決断できない日本人が増えている。それは決断するのに必要な“思考の瞬発力”が欠けているからだと木下氏はいう。判断し、決断する能力はなにもリーダーばかりが必要なわけじゃない。この会社でいいのだろうかと悩み、愚痴をいいながらも定年まで働き続ける会社員が一体どれだけいることか。「決断する時には捨てることも大事だが、結局、判断する力も捨てる勇気もないからいつまでも現状維持。しかし、若いころから決断したり、選択したりする局面にたくさん立たされてきた人は判断がいつもシャープだ。そうした経験を積むのは若ければ若いほど、思考力が柔軟でいい」。だから木下氏が始める「ビズクエスト」は子どもを対象にする。
3.木下氏は今夏、子どもたちが遊び感覚でビジネスを学べるプロジェクト「ビズクエスト」を始動させる。子どもたちは自分でものを仕入れたり、売買したり、利益を管理したりする体験を重ねていくが、ユニークなのは、まずは彼らになにも教えず、自力で考え、ときに失敗し、改善するというプロセスを踏ませることだ。「自転車も、実際に乗ってみなければ走れるようにならない。知識ゼロの状態から未知のことに取り組むのが教育の本質だと思う」と木下氏。当初は都内の子どもを対象に小規模でスタートするが、「明治維新もはじめは国民の0.012%しか関与していなかったと言われている。小さな動きでも継続すれば、やがては世の中を変えるものになるはず」と話す。
4.「いずれビズクエストを東京から地方へ広げたい。地方にビジネスリテラシーの高い人が増えれば、地方は自立の道を歩めるはず」と語る慶應義塾常任理事の國領二郎氏。現在、国から補助金が落ちて来るのをじっと待ち、それにぶら下がっている地方都市が非常に多く、これが現在、日本における地方創生を阻んでいると指摘する。「開発が成長を呼ぶと勘違いしていて、東京並みの巨大な開発をやろうとするから、採算が合わずに失敗する。でも補助金でカバーできるから赤字に苦しむこともない。この現状を変えるには、義務教育の段階から子ども達にお金や組織、リーダーシップについて教えること。そうしたスキルを持った人が市民全体の1%を超えたら、日本の地方都市はもっと変わる」と木下氏もいう。
5.かつての日本では、地方こそ商才溢れる起業家達が多く活躍していて、たとえば江戸時代の北陸は北前船や薬売りなどのビジネスで一大商圏を築いていた。しかし、こうした逞しい“地方スピリット”は、いつしか政府からの補助金という“麻薬”で麻痺してしまい、みずから考え、現状を変えるという気概も失われてしまったようだ。待っていれば頭上の木から甘い果実がふってくるのだから、あえてその場を離れ、果実を探しに森へ入る必要もない。だがもし木の根が腐り、まもなく倒れることに気づく人がいたら−。彼はおそらくしがらみや馴れ合いが複雑に絡み合う密林へ足を踏み入れ、新たな果実を探しはじめる。そして、その閉ざされた世界へ踏み込んだ先で見つけるものは、かつて活躍していたアントレプレナーたちが築いた、大文明の遺跡かもしれない。