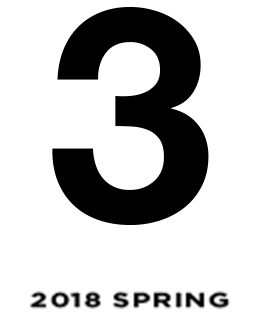青井 茂 株式会社アトム 代表取締役

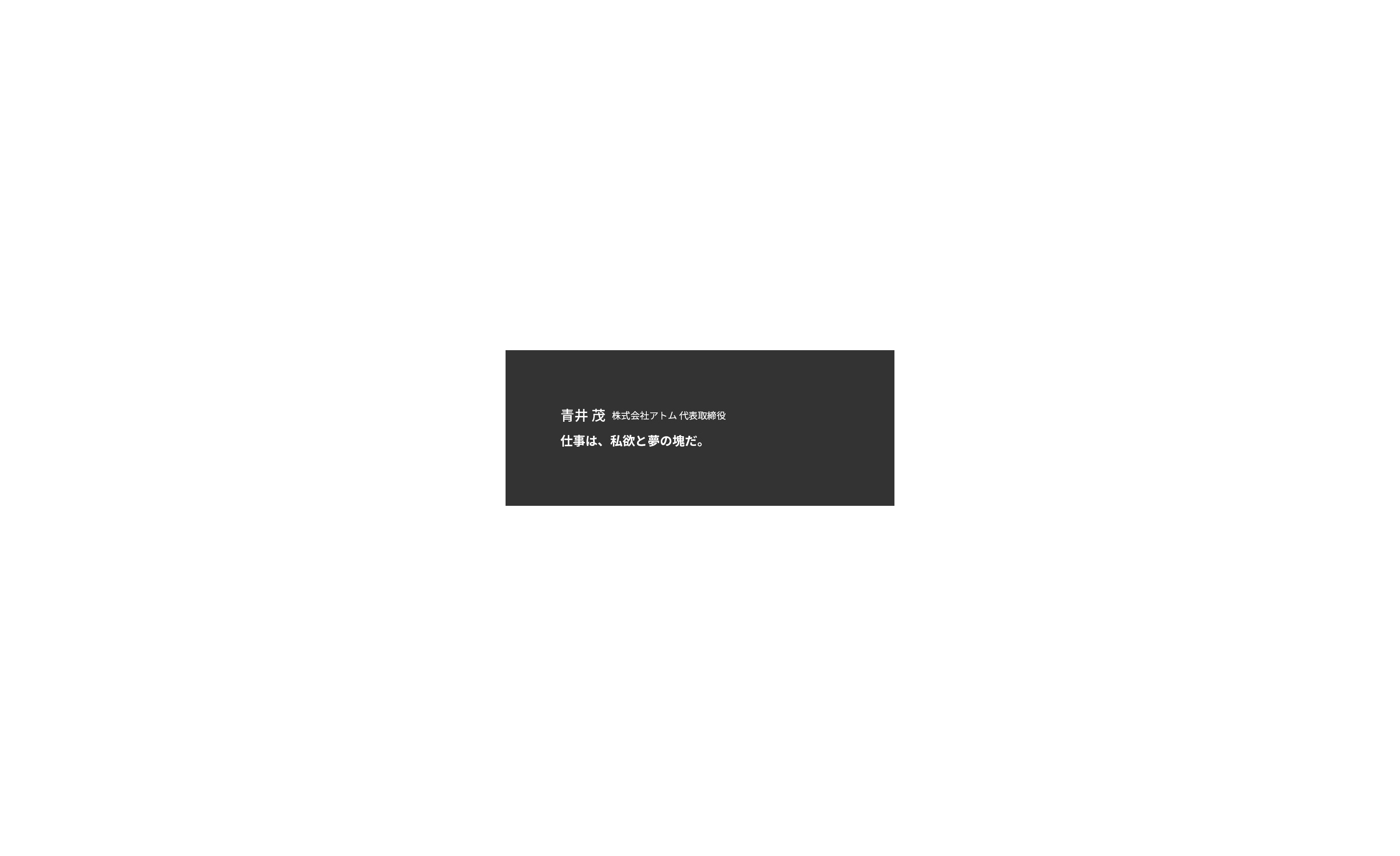
働くことを面白くする方程式とは、(1%の運+99%の縁)×夢である。
『24時間戦えますか』というフレーズとともに、黄色いラベルの栄養ドリンクが流行ったのは、約30年前だ。CMでは残業疲れのサラリーマンが、道を歩けば銅像にぶつかり、電車に乗れば降り損ね、ゴミの代わりにカバンを捨てた。多少の脚色はあったとしても実際、当時の山手線は毎朝そんなサラリーマンを大量に運んでいたし、金曜日の夜になれば、有楽町や新橋のガード下は夢を語り、くだを巻くスーツ姿の男性で溢れていた。あれから30年。スマホやPCは瞬く間に進化して、日本人の生活は大きく変わった。今でもどうして山手線の混雑だけがあの頃のままなのかと、とても不思議だ。
僕は20代の前半、コンサルティングファームで働いていた。祖父は月賦百貨店の丸井を創業したが、周囲から跡を継ぐことを指示されたことはなかったし、僕にもそのつもりはなかった。会社ではとにかく必死に働いた。業務に関係のある新聞記事を切り取ってコピーすることから1日が始まって、会議ではほとんどわからない業界用語に頭を抱えた。でも、ハナキンに飲むビールが最高においしかったのは、今でもよく覚えている。その後、官製ファンドの事業再生会社に転職し、ここでも昼夜なく働いた。徹夜も当たり前だったけれど、もの凄く楽しかったのはなぜだろう。くだらないことやバカバカしいことは山ほどあった。横車を押すような無理難題をふっかけられることもあった。それでもみんなで頭を付き合わせ、愚痴を言いながらも必死にアイデアをひねり出すことは楽しかったのだ。
そんな中、30代のある日、僕は草野球の試合中に大怪我をした。何度も手術を繰り返し、1年以上松葉杖の生活を余儀無くされた。働くことも出来ず、毎日自宅で過ごすしかなかった。Amazonだけが友達で、毎日配送されてくる本が僕と外の世界を繋いだ。絵本から文学作品、更には図鑑までなんでも読んだが、不思議なことにビジネス書はまったく手にしなかった。怪我が少しずつよくなるにつれて、僕の心も前向きになってきた。治ったら、どんな仕事をしてどんな風に生きようか。それまでは目の前にあることを、とにかく一所懸命こなすことしかできなかった僕が、これからどう歩み、どう人生を終えるのか、考えるようになったのだ。
10代のときに読んで以来、たまたま手にした祖父の伝記がきっかけで、僕は祖父が創業した会社のひとつであるアトムに入った。不動産事業は経験がなかったが、これまでの社会人としての経験は確実に役立った。何より、祖父のDNAが受け継がれたこの会社で、祖父を感じながら働くことは、想像以上に責任があり、刺激的だった。祖父は日本初のクレジットカードを発行したが、その背景には顧客への信頼があった。商売を拡大することで、頑張ってくれている社員に報いたいという気持ちもあっただろう。とにかく祖父は、相手が社員でもライバルでも周りを大事にする性格で、まさに「男から愛される男」だったのだ。僕が生まれる前に祖父は他界したので、残念ながら会ったことはない。だが、仕事で悩んだら、「祖父ならどうするだろう」と考えるのが、今では僕の習慣だ。
祖父が働いていた頃と今では、社会の構造はまったく違う。人々のライフスタイルも流行も価値観も、何ひとつ同じではない。世の中は常に変化していて、インフラもIT環境も整った。街も経済も社会のルールも、ひとまずは及第点まで到達した。だが、祖父の時代にあって、現代にないものがあるとしたら、それはたぶん「夢」だと思う。祖父の時代は、戦後の焼け野原からの復興期で、誰もが強い日本を目指してがむしゃらに働いた。いわばそれが全員共通の夢だったからだ。だが僕らの時代には、すでに目指すべき日本は確立されてしまっている。ITの発達により、個人の視点はものすごく近眼的になり、視野は急速に狭くなった。昨日の常識が今日覆されるかもしれない不安定な現在では、未来を描くことも難しい。しかしこんな時代だからこそ、人は夢を持つべきだ。青臭いかもしれないが、堂々と夢を語れない世界では、僕らはきっと行き詰まる。人は誰でも暗闇の前では足がすくむ。だがそこに夢という光がさせば、おのずと足は進むのだ。
団塊とか、バブルとか、ゆとりとか、さまざまな言葉で僕らは世代ごとに分断される。社会では個人主義が尊重されて、利己的な個人、あるいは匿名的な集団が急激に力を持った。しかし本来、世代が変われば趣向や思考は違って当然で、出会いという化学反応こそ、世の中を変えていく起爆剤になるのだと思う。人生の中で、親しく会話をする人と出会う確率は2千400万分の1、友人と呼べる人と出会う確率は2億4千万分の1と言われるくらい、人の縁は天文学的な数字によってドラマ化される。その縁を逃さず育てるために必要なことは、自分の「旗」を掲げること。「僕にはこんな夢がある。こんな生き方がしたいんだ」と書いた旗を振れば、必ずそれに共感する人が集まってくる。反対に、僕が誰かの旗を見つけ、その人の挑戦する意欲に共感して声をかけることもある。実際、僕がオーナーを務めるコートヤードHIROOは、そういう人たちの集合体だ。僕はそんな風にあちこちで旗が振られ、互いに引き寄せあう世の中こそ、本物の個人主義が浸透した社会だと思う。
『24時間戦えますか』の時代は、すでに遠い。私生活を犠牲にして、闇雲に働くことは決して良いわけじゃない。けれど、みんなで頭を並べ、ああだこうだ言いながら仕事に没頭するのは、間違いなく楽しい。考えてみれば僕が20代の頃、過酷な労働の中でも仕事が楽しくて仕方なかったのは、自分の中で、わずかでも夢を描くことができたからだ。まだ成熟しきれていない若者にも、自分で判断し、行動する責任と権限が与えられた。数字で優秀かどうか判断される窮屈さがあったとしても、誰もが夢を持ち、酒を飲みながらたわいもないことを語り合えた。そんな毎日が、仕事を現実以上に楽しく思わせていたのだろう。今、目の前にあるリアルな社会をみんなで共有することは大切だ。だけどもしかしたら、まだここにない未来を誰かとシェアし、共に夢を見ることは、もっと世の中を面白くするのかもしれない。
働く動機や夢が、超個人的なものでもいいと思う。私利私欲と仕事を混同したって、自分の夢に共感してくれる人との出会いがあり、新しい何かが生まれたら最高だ。ちなみに僕の夢は将来、プロ野球チームのオーナーになることだ。球場を作り、選手が集まり、開幕戦でスタンドから大声で声援を送るなんて、想像するだけで興奮する。孫やひ孫に「この球団はわしが作ったんだよ」と説明しても、最初は「まさかぁ、そんなの嘘だ」と相手にされないかもしれない。でも、よく調べたらそれが真実だとわかり、「じいちゃん、すげえ!」ってみんなが目を丸くする。そんなシーン、最高じゃないか。僕にとってはその夢の存在が、働くために必要な「黄色いラベルの栄養ドリンク」なのだ。
村田諒太 と 盆栽


ロンドンオリンピックで金メダルを獲得、現WBA世界ミドル級王者である村田諒太。熱い戦いに身を投じながらも、孤高の哲学者のような佇まいを見せるこの男が、今回、初めて盆栽を体験。そこに見えたものは、静寂の中に浮かび上がる、戦う男の冷静な情熱だった。
村田は、父の田舎である岡山を思い出すと言って、橙色の実をつけたキンズの苗を手に取った。そしてその苗木を鉢に植えた。十分に根をほぐし、栄養が行き届くように根の先端を大胆に切り落とす。村田は「こんなにバッサリ切り落としていいんですか」と驚きながら、「本当に必要なものって、意外と少しだけなんですね」と呟いた。
「盆栽は6年やって、初めて一人前と言えるみたいですよ」。葉をつまんで鋏を入れ、木の体裁を整えながら村田は言った。「僕は中学一年生のころからボクシングを続けているけれど、まだ一人前という感じがしないのに」。ロンドンオリンピックで金メダルを取り、昨年はWBA世界ミドル級王座も手にしたのに、この男はまだ一人前でないと言う。
村田はこれまで2度、ボクシングを辞めている。1回目は北京オリンピックの出場権を取れなかった時、2回目はロンドンオリンピックが終わった時だ。1度目に引退したあとは、ボクシング部のコーチを務めながら大学職員として働いた。だが、元部員の不祥事をきっかけに1年半ぶりの現役復帰を決意。「部が活動自粛になり、降格処分をくらったんです。でも、全日本選手権で優勝できれば名誉を回復できるかもしれない、それなら俺が一肌脱ごうと思って試合に出たら、勝ってしまった。北京に行けなくて引退したけれど、なんだまだやれるじゃないかって、復帰したんです」
引退を決めた時は、もう海外の一流選手に勝てないと思った。オリンピックで金メダルを取るという夢は叶わなかったが、無理に続けても仕方がないと割り切った。だが途中で折れたままだった夢の木は、心でくすぶっていたのだろう。現役に復帰すると決めた途端、一気にギアが切り替わった。そして、世界一への階段を猛スピードで駆け上がった。
「盆栽って初めてやったけれど難しいんですね。でも、いい具合に集中できる。座禅を組むみたいな感じです」。村田はさまざまな角度から木を眺め、鋏で形を整えながらそう言った。「無心になろうとしても難しいですよね。ボクシングでもそう。いつも人の目を気にしてしまう。勝って当然というみんなの期待に応えなくちゃって、自分を追い込んでしまうんです」
ボクシングを始めた時は、「強くなりたい」「勝ちたい」という一心だった。打たれても打たれても、なお相手を倒すべく踏み込んでいく、これほどまでに熾烈で過酷なスポーツは他にない。だからこそ、世界の中心に自分を据えるような、自己中心的な心構えも必要なのだ。しかし皮肉にも、勝てば勝つほど世間の目が気になってくる。チャンピオンとしての自分は、ちゃんと周囲の期待に応えているか。
「『人』の『間』と書いて人間って読むのだということを、しみじみと感じます」。村田は静かにそう言った。
勝つほどに世界は広がり、世間の期待が村田に重くのしかかる。自分という本質を置き去りにして、周りが「村田諒太」という架空の人物を作り上げる。その乖離に村田は長く苦しんだ。それが変わったのは、2 0 1 6 年1 2 月3 0日。有明コロシアムでブルーノ・サンドバルと戦ったときだ。「試合の前、ホテルの部屋で不安と緊張から独り言が止まらなかったんです。『不安だ』『なんで不安なんだ』『負けたらみんなに申し訳ないじゃないか』『周りに迷惑がかかる』『そんなの関係ないだろ』『いや、関係なくねえよ』『じゃあお前、なんのために試合すんだよ』って、ずっと自分に問いかけていました。そして、考えたことをノートに書き殴りました。そうするうち、次第に心が落ち着いてきたんですよ。『どうしたって、やるしかねえじゃん。頑張れよ』って開き直れたんです」。人は、正体が見えないものを不安に感じる生き物だ。それなら、不安を目に見える形で表せばいい。「もちろん、不安の正体がわかったからと言って、恐怖や緊張は消えません。でも、『やるしかねえだろ』って開き直ったら、自分を俯瞰できたというか、遠くから自分を眺められたような気がしたんです」。村田は手の中にすっぽり収まる鉢植えを、両手で抱えながらそう言った。
自分より強そうな相手と戦うこと。絶対こいつには勝てないだろうという予想を裏切って勝利すること。それがボクシングの魅力にとりつかれた原点だと村田は言う。ボクシングをはじめて約2 0年。それだけ長い間、シビアな世界に身を置き続けたのは、一体なぜか。
「人間は、誰もが神様から才能を与えられていて、それが僕の場合はボクシングだった。だからそれは絶対に使わなければいけないと思うんです」。かつて高校時代の恩師は、部活内で揉め事が起こり、「辞めてやる」と部室を飛び出した村田に「逃げるとか辞めるとか、そういうことは自分の才能や能力を捨てることだ」と言った。「お前の拳は、あらゆる可能性が秘められた拳なんだ」。だから村田は決して逃げない。これしか道はないのだと、腹を括ってリングにあがる。「人間って、なんのために働くかとか、どうしてわざわざしんどいことをするかとか、つい理由を考えがちだけど、本当は理由なんてどこにもないって思うんです。僕がボクシングをしているのも、自分が挑戦する姿を見せることで誰かの励みになればいいとか、かっこいいことはいくらだって言える。でも本当は、そんな意味づけなんて必要ないって思うんですよ」。じゃあ一体、村田に厳しい練習をさせ、極度の緊張とプレッシャーの中、世界の強敵に挑ませるものは何なのか。その答えを探すため、村田はボクシングを続けるのだ。
「精神科医であるフランクルは、『人生に意味を求めてはいけない。人生からの問いかけにどう答えるかが大切』と言いました。つまりこれは、『今』をきちんと生きなさいっていうこと。僕にとっては一戦一戦全力で戦うことが、『今』を生きるっていうことなんです」。ボクシングという道を、重い荷物を背負って歩く旅人みたいですねと村田は笑った。
鉢に苔を植え、盆栽の作業は終わった。「盆栽って、木の根っこが一番の見どころで、その部分に日光が当たらないと木は成長しないんだそうです。だから、本当は根っこの際まで苔を植えちゃいけないのに、僕はつい見た目を気にして、ギリギリまで植えてしまった。もう一度、植え直したいけれどやり直しはきかない。人生と同じですね」。これから毎日手入れをしますと、村田は部屋をあとにした。盆栽には、どこまでいっても完成がない。葉が伸びれば鋏を入れ、実がなれば摘み取って来春の花を待つ。村田にもボクサーとしての完成はなく、どれだけタイトルを手にしようとも、また、どれだけ恐怖とプレッシャーに襲われようとも、ただ日々の着実な歩みだけが明日の村田を作るのだ。
Home in the Expanded Field



孤高の営みであるアートを、集団で創ること。
それは世界観の共有であり、自分への挑戦でもある。
「アートとは」という問いに対し、「自分の感情やアイデアを形にし、他者とコミュニケーションするための手段」と語るフレイヤさん。18歳の頃、”正確に”“正しく”絵を描く技法を学ぶために、動物や人体の解剖図などを描き始めた。
「ケンブリッジ大学では、頭蓋骨から人の顔を復元する方法を学びました。これは英国外科医師会(RCS)で、外科医が手術を練習するために必要な、人間の頭部ダミーを作る仕事につながりました」
そのほか、セントラル・セント・マーチンズで「芸術と科学」コースにも在籍。現代科学理論と研究に基づいて作品を制作するために、科学研究所との共同作業にも取り組んだ。
「私の作品にとって、自然世界の構造や機能は注目せずにいられない主題であり、今でもそのパターンとリズムが制作の基本になっています」
作者の意思や意図が見る人のこころを捉える「アート」を相対的なものと考えれば、冷静な客観性の上に成り立つ「自然科学」は絶対的なものである。これらは一見、相反するように思えるが、彼女はふたつを融合させたところに、独自の世界観を見つけている。
「アートを制作するには、3つの段階があります。まずは、アイデア。何もない空間に、私は何を作りたいのか、そして、『ひと』は何を見たいのか。次に、それらを映像化してラフデザインを起こします。それから、制作に入ります」
ここからは究極的な個人体験。アイデアの段階では『見るひと』を想定しても、いざ作り始めたらもう誰も彼女に影響を与えることはできない。
「だからこそ作品を通して、自分のアイデアをひとと共有できることに、アートの魅力があるのだと思います」
考え、作り、表現する。そうした個人体験が優れたアートを生み出す力になるなら、「アートとは、孤高の営みである」となるだろう。しかし、と彼女は言う。
「たとえば、他のアーティストとグループで展示をする場合、みんなでテーマを共有することにより、創作のプロセスが進化したり、変化したりします。いつもと違ったやり方で創り、新しい環境にも馴染まなければならない。みんなで創り上げることは確かに難しいけれど、とても刺激的で、魅力があります」
過去にはイギリスのナショナルリテラシートラスト(National Literacy Trust)とコラボし、50人のアーティストが50人の作家とともに、出版社が販売する本のシーンをアート作品として制作するという、大規模な企画に参加したこともある。また、コートヤードHIROOを舞台に、彫刻家・画家の母と、建築家であり、レコードジャケットデザイナーでもある父とともに、展覧会を開催したこともある。他者との共同で現れる、個人的な創作活動ではなし得ないなにか。それこそ、その瞬間しか現れない、リアルなアートの価値なのだ。
「今回、コートヤードHIROOで開催するグループ展は、ロンドンの芸術大学出身者7人によるもの。在籍した時期は異なりますが、みんなで『家』をテーマにさまざまなアート作品を展示します」
「家」という、誰もが共通してもつモチーフは、実は、非常に儚いもので、もしかしたら想像上の産物かもしれない。都市化が進んで世界がボーダーレスになり、人の移動が盛んな現代ならなおさらだ。その「家」を7人のアーティストがどのように表現するか。彼らの個人的な経験が、それぞれ有機的に結合をした果てに、まったく新しい「家」の像が現れる。
木下斉


その働き方は、確かに自分で選んだのか?
「働く」という行為を大きく分類すれば、「被雇用者として働く」「独立して働く」という二つになる。雇われるか、自立するか。これは人生の中で大きな違いだ。
「日本ではこの半世紀で自営業主や家族事業従事者が急速に減少。今では被雇用者が9割を占めています」
まちづくりや地方創生に取り組み、商店街の活性化なども積極的に行っている木下斉氏はそう語る。
1953年には全就業者の中で被雇用者の割合は約4割だったが、その数字は急激に伸び、2016年にはほぼ9割。自営業主はなんと1割にも満たない。確かに、1980年代後半から90年代初めまでのバブル期は、潤沢な資金と莫大な投資に支えられ、多くの会社が勢いよく業績を伸ばした。接待だ、ボーナスだと、ヒラ社員であっても羽振りがよかったから、「卒業後は会社員」と考える人があとを絶たなかったのはわかる。だがバブルが崩壊してもなお、「会社に属したい」という人が増え続けているのだ。「独立しても雇われても、先行きは不透明。それなら、雇われていた方がまだ低リスクだ」。そう考える人が多いのだろう。しかし、果たしてその働き方は本当に自分の意志で選択したと言えるのか。
モラトリアムは、まだ、静かに増え続けている
高校や大学を卒業すると、多くの人が就職先を考える。目の前に見えるのは、一本のレール。一度、走り始めたら、そのレールからはみ出すという考えはほとんどない。
「しかし、人間には選択権があります。集団で能力を発揮し、企業という後ろ盾を持って、スケールの大きなビジネスを動かすことが得意な人もいるでしょう。しかしもし、独立とか起業とか、他の選択肢と早いうちに出会うことができたら、そして、そっちに自分の適性を見つけることができたら、人生は違ったものになったかもしれません」
一昔前、モラトリアムという言葉が流行した。卒業前の学生は人生という大海原へ乗り出すことを躊躇して、いつまでも猶予期間の中にいた。それは、選択肢をどこにも見つけることができなかったから。手札がないので、初めの一歩をどう踏み出したらいいのかわからなかったのだ。現在、新卒者が三年以内に退職する確率は約3割。そのうち、約12%が一年以内に辞めている。モラトリアムの時代は終わっていない。今もまだ、会社という空間に身を置きながらも、猶予期間を過ごす若者たちは増えている。
組織の中から、組織を作る人間は生まれない
生活費などのリスクが低い学生時代に、商売をしたり、事業を立ち上げたりする経験が役に立つ、と木下氏は言う。事業のリテラシーが磨かれ、貨幣経済をベースにする社会での共通言語をもつことができるからだ。
「一度でも事業経験を積んだ人間なら、会社員であろうと公務員だろうと、新たな価値を作ったり、限られた資金の中で最大限のサービスを作ったりすることが可能になる。そうすれば、より生産性の高い仕事につながります」
事業の立ち上げを経験し、自分はやっぱり組織で働くことが向いていると思ったら会社で勤めればいい。大切なのは、「自分の意志でその道を選んだ」という事実だ。組織の中からは、組織を作る人材は生まれない。一度、大海へ飛び出してこそ、知恵と知識は養われるのだ。
「稼ぐ」と「働く」は、イコールだ
経済という言葉は、そもそも「経世済民(世の中をよく治めて、人々を苦しみから救う)」という言葉を起源にしている。その意味を取り違えているのだろうか、稼ぐことは「よくないこと」「卑しいこと」と思う人は少なくない。だが、果たして本当にそうだろうか。経済と経営から成り立つ現代社会で生きている人間にとって、稼ぐことは悪いことでも卑しいことでもない。むしろ、労働の対価として金銭を得ることは、働きが認められたということ。社会に価値のある労働でなければ、稼ぐことはできないのだ。「経営はお金の話だけでなく、組織運営や人事管理なども幅広く考える必要があり、その結果、お客さんから対価を得る。こうした当事者意識や事業者意識は、いつ、どんな職業に就いていても、必ず役に立つはずです」
学びながら、ビジネスを身につける子どものための「ビズクエスト」、始まる
たとえば、90円で仕入れたりんごを100円で売ってみる。どうやったら、もっとたくさんのお客さんに買ってもらえるだろう。どうやったら、お客さんに喜んでもらえるだろう。そんなことを考えながら、子ども達がリアルにビジネスを学ぶのが、木下氏の企画する「ビズクエスト」だ。街そのものをキャンパスに、子ども達はチームを組んで、事業に必要な基礎スキルやリーダーシップを学んでいく。考え、行動し、振り返る。その過程で、子ども達は柔軟な思考力を武器に、ビジネス創造の種をまく。2018年、コートヤードHIROOで「ビズクエスト」が始動。プロジェクトの模様は、次号以降で紹介する。